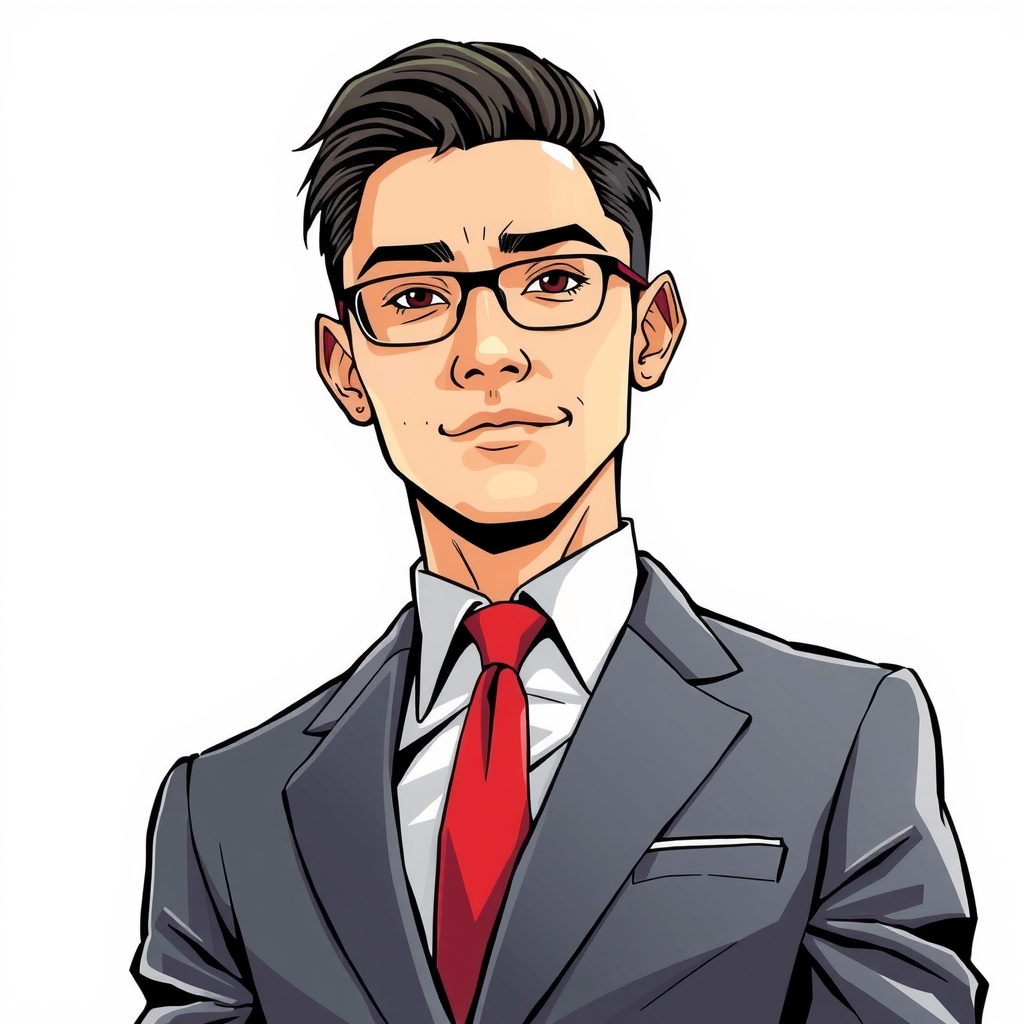
こんにちは。不動産営業について発信している律です。
プロフィールはこちら
本ブログは読者を「売れる不動産営業マンに進化させる」という目的のもと運営しております。
本ブログのコラム記事では、主に不動産・建築関係のニュースを取り上げ、地域に与える影響や、今後の展望を個人的な意見を交えて紹介していきます。
時事ネタの一つとして、気軽に読んでいただければ幸いです!
↓先日こんな記事が出ていました。
【参照】
日本経済新聞 京阪樟葉駅、28.7%が「駅までバス」 関西で比率トップ
(京阪電鉄・樟葉駅、28.7%が「駅までバス利用」 関西で比率トップ - 日本経済新聞)

不動産営業において「徒歩○分」という条件は、長らく最重要視されてきました。徒歩10分圏内の物件は「資産価値が下がりにくい」「人気が落ちにくい」といった理由から、顧客にも営業にも好まれる傾向があります。
しかし、最近のデータからは、“徒歩圏”の優位性を見直す必要性が見えてきます。
バス利用率28.7%――関西トップの「樟葉駅」
先日公表された調査によると、**京阪樟葉駅のバス利用率は28.7%**と、関西主要駅の中で最も高い数値を記録しました。
これは、単に徒歩が不便ということではなく、「バスが非常に機能しているエリア」であることを示しています。
つまり、「駅から遠い」ことが、必ずしもネガティブではないということです。
駅から徒歩25分、それでも住み続ける理由

樟葉駅周辺で象徴的なのが、1960〜70年代に開発された男山団地。駅から徒歩だと25分ほどかかりますが、現在でも約2万人が暮らす大規模住宅地です。
それを支えているのが、京阪バスによる1日481便の路線バス。駅から団地まではわずか10分。特に高齢者の多いエリアでは、「歩けるか」よりも「乗れるか」の方が重要です。
学生需要と生活動線の掛け算
さらに、樟葉駅周辺には摂南大学や大阪工業大学のキャンパスがあり、学生の約5割が駅からバスを利用して通学しています。
また、駅前には大型商業施設「くずはモール」もあり、通勤・通学・買い物すべての目的地がバスを起点とした生活動線上に配置されているのが特徴です。
つまり、ここでは「徒歩の距離」ではなく、「生活全体としてのアクセス性」が住まい選びの軸になっているのです。
「徒歩圏外」の物件を、どう見るか
このようなエリアでは、物件が徒歩15分や20分であっても、販売可能性は十分にあります。重要なのは、そのエリアに次のような条件があるかどうかです。
これらが揃っていれば、徒歩圏でなくとも「売れる理由」があるエリアと言えます。
【個人的見解】
個人的には、「徒歩圏じゃない=不利」という常識は、すでに崩れつつあると感じています。
実際、樟葉駅のようにバス網が充実していれば、徒歩15分以上の物件でも十分に選ばれます。特に高齢者や学生など、徒歩よりも効率的な移動手段を求める層が多い地域では、バス便こそが生活インフラです。
営業としては、「徒歩何分」ではなく「どう移動するか」という生活の動線にまで目を向けることが、今後ますます重要になると考えています。
まとめ
樟葉駅の事例は、徒歩圏外の物件にも「選ばれる理由」があることを教えてくれます。
特にこれからの営業に求められるのは、表面的な数値にとらわれず、顧客の生活全体を見据えた提案力です。
距離を売るのではなく、生活を支える導線を売る営業へ。
それが、これからの不動産営業に求められる進化だと言えるでしょう!
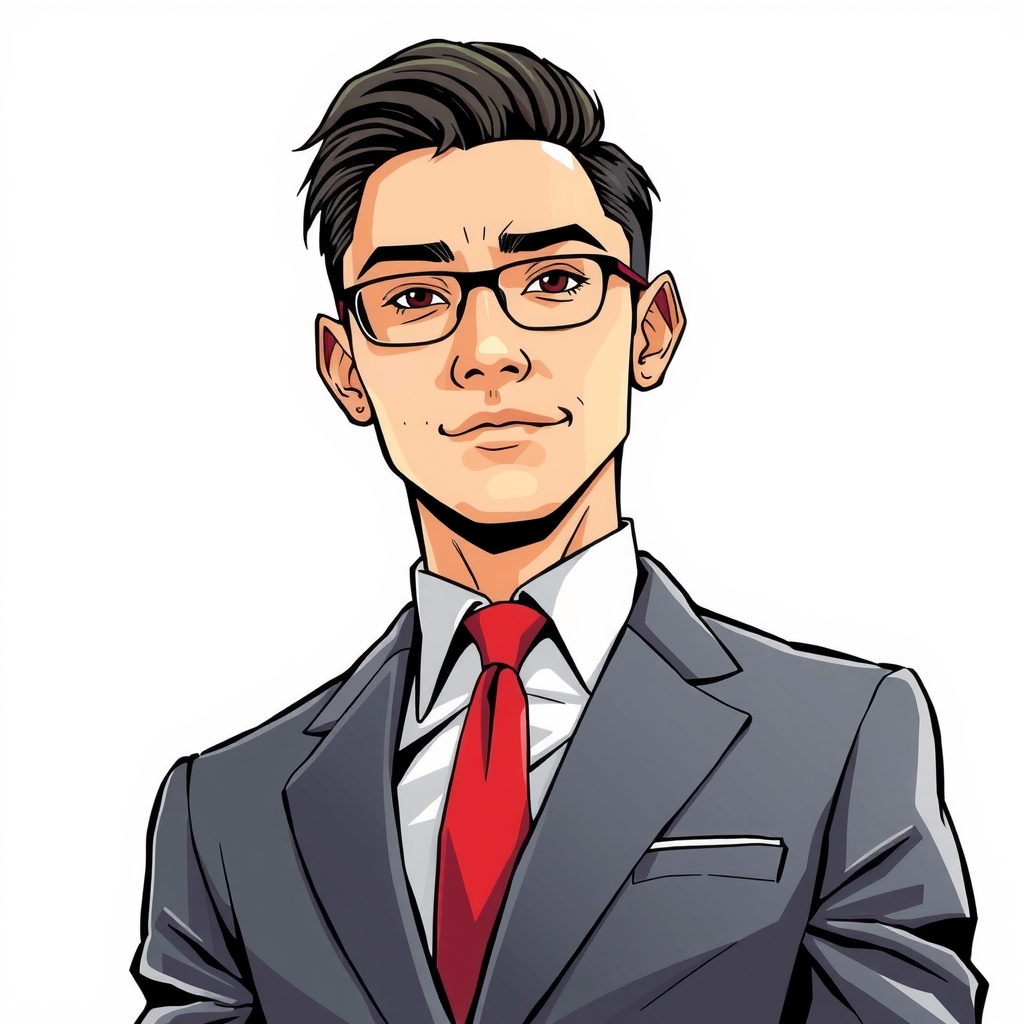
本ブログは、不動産営業マンを成功させるためのバイブルを目指して運営しています。
今後も有益な発信・イベントを多数打ち出す予定なのでSNSも併せてフォローしてください!