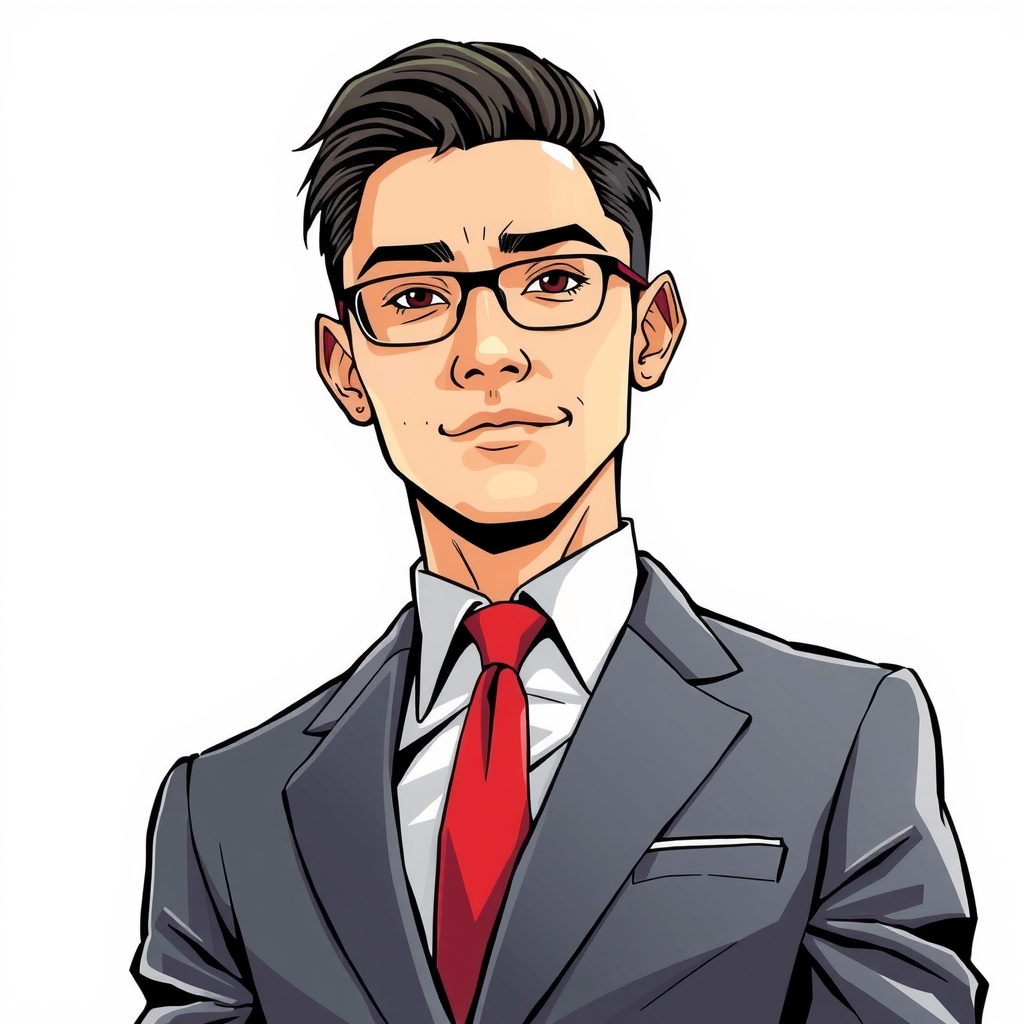
こんにちは。不動産営業について発信している律です。
プロフィールはこちら
本ブログは読者を「売れる不動産営業マンに進化させる」という目的のもと運営しております。
今回は不動産営業マンが理解しておくべき顧客心理について解説していきます!
きれいな身なり、丁寧な接客、親身なアドバイス。これらを全て実践しているのにお客様がなかなか前のめりになってくれない…。
少しづつ、商談に慣れてきた若手営業マンが直面する壁の一つです。
駆け出しのつたない言葉遣いや、知識が浅かったときの方がお客様と密にコミュニケーションを取れていたのに、なぜかレベルアップしたはずの今の方がコミュニケーションに苦労をしている。
私も商談経験をそれなりに重ね、ヒアリングや物件説明にいっぱいいっぱいになっていた状態から卒業した際、商談をコントロールしようとすればするほど、お客様からの拒絶反応を感じるようになりました。
実はこれには理由があります。
それはお客様の売り込まれるのを避けたいという防衛心理です。
たしかにあなたのレベルは着実にアップしています。しかしそれが良くも悪くも、あなたの自信や余裕を生んでしまっているのです。
見た目が若めのこなれた営業マンが担当となったお客様は、「売り込まれたくない」や「損をするのではないか」と身構えてしまいます。
今回はそんなお客様の防衛心理を緩める方法を、具体的な営業ツールを使って解説していきます。
本記事を読めば、お客様が親身にあなたのトークに耳を傾けてくれるでしょう。
そしてあなたのトークは、よりお客様に響きやすくなることが期待できます。
それでは最後までご覧ください!
もくじ
お客様の心理状態について

この記事を読んでくださっているあなたは、最近お客様との間に壁を感じるようになってきたはずです。
まずはこのお客様との壁について解説していきます。
お客様と営業マンの信頼関係(心理状態)については大きく3つあります。
お客様>営業マン
お客様がこちらに対して壁を作ってしまっている状態です。
たとえば関係性の薄い知り合いや、ちょっと怪しいと感じる人の言葉は話半分で聞きながら、どこか俯瞰的にその場を見ようとする自分がいると思います。
こちらの問いかけに素っ気ない返事をしたり、相づちが少ないときはこの状態を疑いましょう。基本的にこの関係性を解消しない以上、どれだけ自信のあるトークをしても、そもそもの関係性が出来上がっていないため、威力は半分かそれ以下にまで下がってしまいます。
そのため、ここでの断り文句は「また何かあったら連絡します」や「検討してみます」などグリップの弱い着地になってしまいます。
最悪、連絡無視や再来の無断キャンセルが起こってしまい、担当としてのあり方について上司からお叱りを受けるかもしれません。
お客様=営業マン
お客様からの質問に受け答えができて時折、商談中でも笑顔がこぼれるような関係性がこちらです。
担当者としての印象は良いため話は弾むのですが、具体的な提案やクロージングに入ると決断しきれない状態が多くあります。
要は決定力に欠けている状態です。
営業マンも途中までは「これはいけるんじゃないか…?」と思ってしまい、舞い上がってしまうのがあるあるです。
しかしそれは、単にお客様の反応が良いだけで本質は物件を気に入っていなかったり、営業マンと半端に関係性が出来上がってしまったがゆえに、きっぱりと断ることができない心理があります。
個人的には前項の状態よりもタチが悪く、苦しめられる営業マンが多いと思っています。
よく言われる一言は「良いひとだったね」「話しやすい人だったね」です。
お客様<営業マン
こちらは完全に営業マン主導で、商談を進めることができている関係性です。
主に下記のような状態にあるとき、その商談はほとんど決まったと言っても過言ではないでしょう。
このようにお客様が物件探しについて"頼ってくれている"、また営業マンの意見に"耳を傾けてくれる"姿勢にあることが我々が目指すべきシチュエーションです。
心理階層について
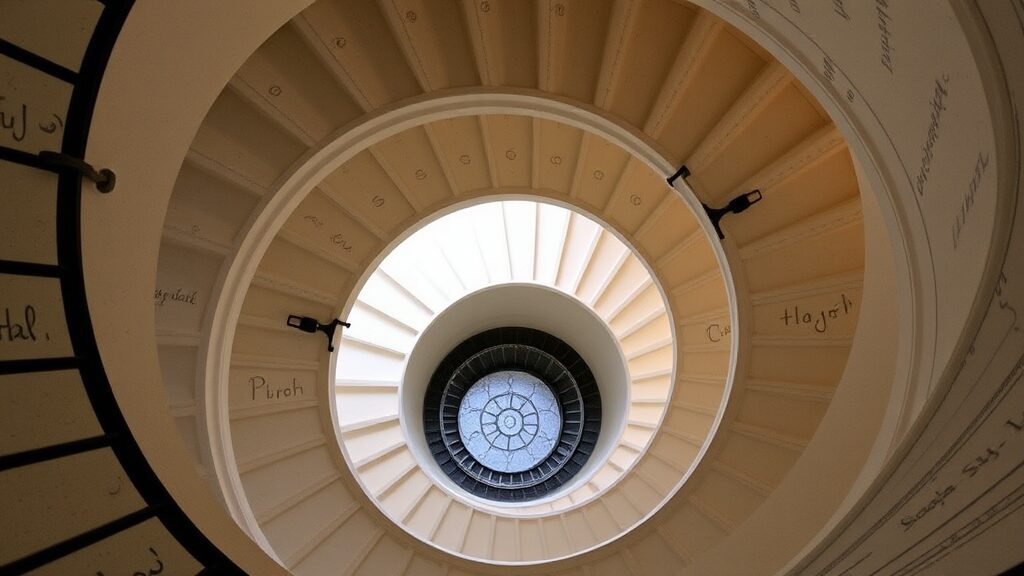
上記の3種類の信頼関係の層を心理階層と呼び、心理階層を上から下へ深めていくことが営業問わず、交友・恋愛・対人関係において重要となります。
そしてこの階層を深めていくのに、有効なものが第三者からの権威性のある情報です。
では具体的に、営業において役立つツールを次項で紹介していきます。
心理階層の深め方
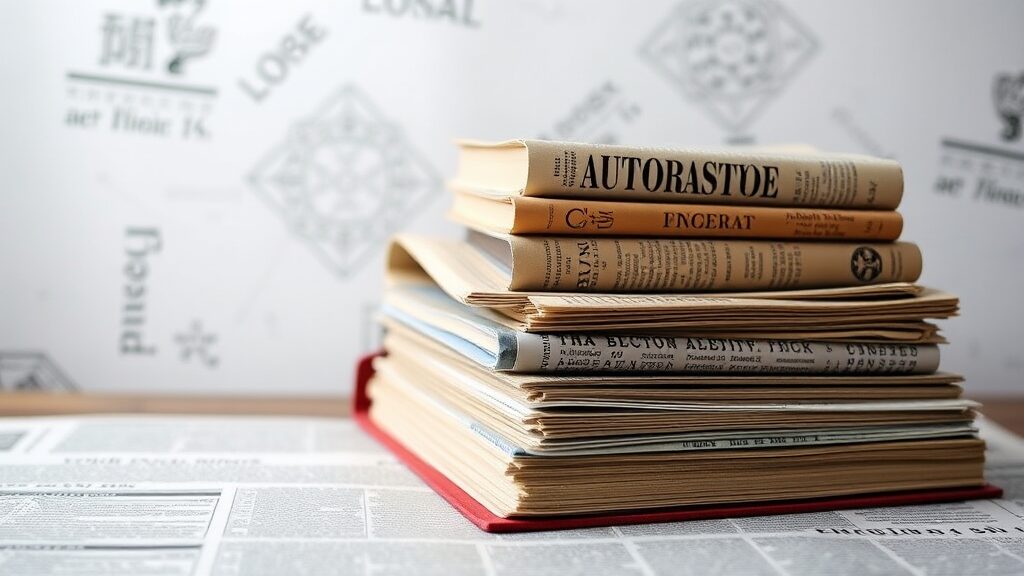
人は権威性のあるモノや情報に弱く、無意識にしたがってしまいます。
ある心理学実験の結果があります。
1963年にイェール大学にて行われた「アイヒマン実験」によると善良な一般市民でさえ、権威ある者の命令があれば他者の命を危険にさらすほどの行動をとるという結果が出ました。
これは被験者を教師、仕掛け人を生徒に分け、生徒が問題を間違えるたびに電気ショックを与えるよう教師は命令を受ける
という内容でした。
結果、40人もいた被験者のうち、電気ショックを与えることを辞退した人はいなかったそうです。
このことから人は権威性のあるものに対抗する力が弱いと考えられます。そしてこれを営業のツールにも応用します。
最もおすすめのツールは新聞記事です。
最近だと"建築資材高騰に伴い、マンション価格も高騰"や"住宅ローン金利の上昇"などが不動産業界でホットなニュースです。
これらは情報番組でもよく流れていますし、すでに家を購入した人たちの間では世間話の一つにもなっています。
今後物件を購入する人にとっては、かなり敏感になっている内容です。
この、その人が気になっている情報 × 権威性の最たる例が新聞記事です。
お客様との商談中、「そういえば今朝の日経新聞の記事で…」と権威性の担保された情報を自然と出せると、お客様の注意を惹けます。
これが増えていくと心理階層の最深部"お客様<営業マン"の構図が完成します。
しかしこのツールを使用する際、2つの注意点があります。
1つ目は権威性集めに躍起になり、不動産情報のスクラップブックを作ってしまうことです。あくまでもこのような情報は"自然と"出すべきです。
たとえお客様のことを思って、それらの情報を集めたとしても待ってましたといわんばかりに、それらを披露すると"売りたい感"が前面に出てしまいます。
冒頭にも述べたように、お客様は売り込まれるのを避けたいという防衛心理を持っています。
その心理を引き起こさせるような行動はしない方が得策です。
2つ目は情報には賞味期限があるということです。
私は月に1冊~2冊は本を読むようにしています。読む本の決め方はわりと直観的で、書店に行き表紙や帯などを見て面白そうなものを
購入します。
しかし、もし同じような見出しや、流し見をしたときの印象がほぼ同じであれば発行日が新しい方を選びます。
なぜならインプットする情報が新しいからです。
何度も重版しているような良書は冒頭に、これは当時の情報である旨や時代に合わせ加筆修正している注釈が書かれています。
実際はそのような書籍は多くありません。
そして私と同じように、お客様の中にもできるだけ新しい情報を求める方もいらっしゃいます。難しいところは"新しい"という感覚は曖昧で主観的であるということです。
これは、その人の業界や職種という周辺環境と、どのような情報であるかという属性の掛け合わせで無数のパターンがあるからです。
以上より私は情報には賞味期限があり、新しいものであるほど効果的だと考えます。
目安としては前週までに出た情報であれば「新しい」と判断しています。
若手が権威性のある情報を駆使することについて

私は若手こそ上記のツールを積極的に駆使するべきだと考えています。
なぜなら、どれだけ優秀な若手でも等しく「業歴が浅い」という事実は変わらないからです。これは初めてお客様と対面したときの信頼できるかどうかという面に大きく関わってきます。
もちろん、営業は素質やセンスに依存するところがあります。
お客様の会社でも若くて結果を出している後輩もいることでしょう。
しかし人は事実を都合のいいように捻じ曲げる性質を必ず持っています。
はじめて会った若手の営業マンに、自身の住まいに関する相談をして損しないだろうかと不安も持っています。
この思い込みからくる偏見や、相手からの見られ方について若手営業マンは強く意識しなければなりません。
ここにおいては、あなたがどう思うかという視点は捨てましょう。お客様がどう感じるかが最重要です。
どうしようもない不条理な現実ですが、あなたはこれを受け入れなければなりません。
そして、それをどう解消しようという考えに切り替わったとき、本当の意味でお客様視点に立つことができます。
私はお客様の立場に立った時、安心できる材料の一つとして新聞記事のような、権威性ある情報を提供することも"お客様のために"必要であると考えます。
まとめ
さて今回はお客様との信頼関係の構築について、構造的な部分と私が考える有効的なアプローチについて解説しました。
現状、具体的な改善策が何も思いつかないという若手営業マンはぜひ一度実践してみて下さい!
ここまで読んでくださったあなたは、いずれ周囲と大きな差を生むことでしょう。
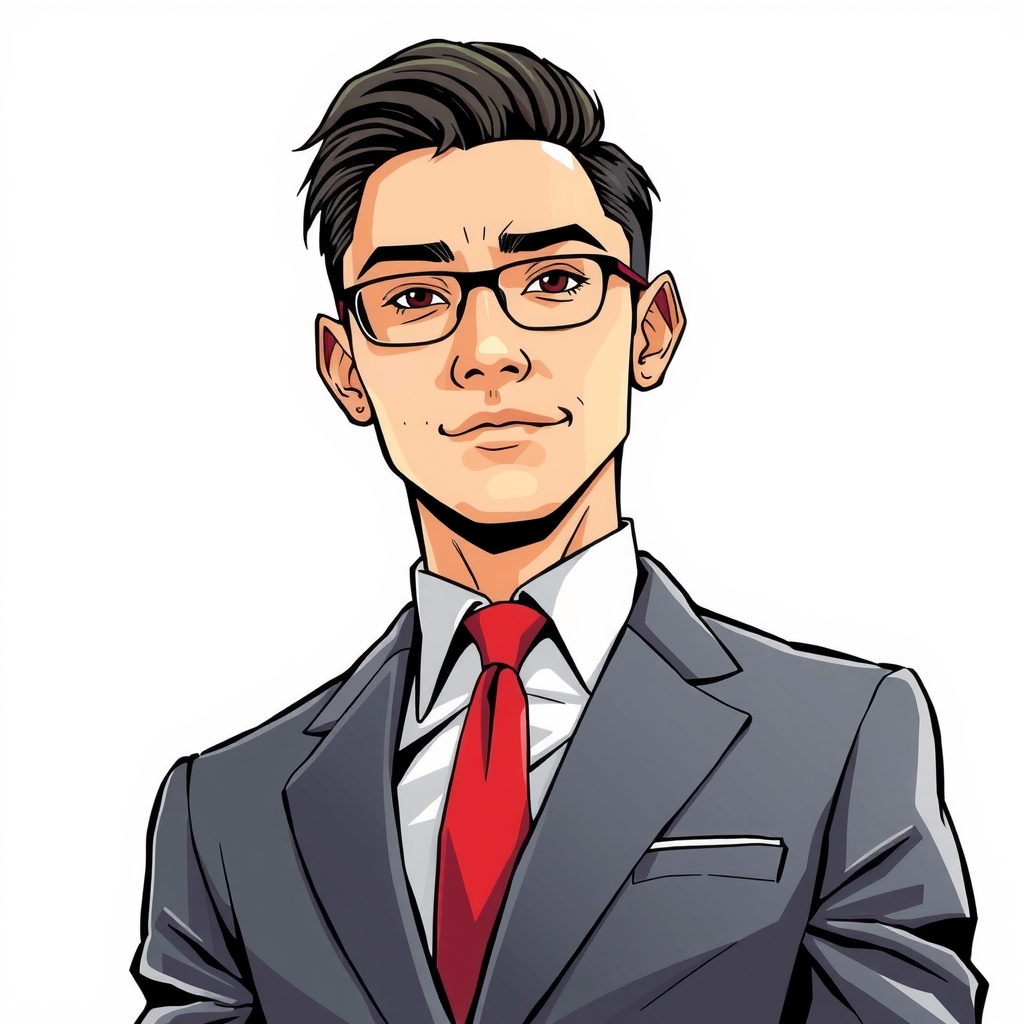
本ブログは、不動産営業マンを成功させるためのバイブルを目指して運営しています。
今後も有益な発信・イベントを多数打ち出す予定なのでSNSも併せてフォローしてください!